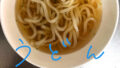建築物の高さの最高限度は殆どが道路高さ制限で決まるといっても過言ではありません。
ここでは道路高さ制限の手順を各ステップごとにまとめておきますのでわからない人でも
試してみてください。
ステップ1 採用する道路の幅員の確認
敷地に接している2以上の場合、道路幅の広い方をとることができる条件の確認です。
(令第132条)求める高さの位置が下記のものが該当します。
- 大きい道路幅の境界線から2倍以内かつ35m以内にある
- その他の道路の中心線から10mをこえるとこにある
注)採用する道路の反対側に公園や川がある場合はその幅も道路幅に含めるので確認(令第134条)
ステップ2 水平距離の算出
道路幅を大きい方で取れる場合は求める高さの位置が境界線から近い方(数値が小さくなる方)で算出して、取れない場合はそれぞれで求めて小さい方を算出する
(道路境界~建築物)+(道路幅)+(道路境界~建築物)+(建築物~求める高さの位置)
道路の反対側に(道路境界~建築物)までの距離を足すので注意してください
ステップ3 高さの算出
水平距離に用途地域により斜線勾配を乗算する
- 住宅系:(水平距離)×1.25
- 商業系:(水平距離)×1.5
ステップ4 道路中心の高さの確認
ステップ3までで求めたのは道路中心からの高さです。ですが、問題では敷地からの高さと出題されるので道路が敷地より低い場合は求めた高さから減算する。(令第135条の2)
高さが1m場合 :1mを減算する
高さが1mを超える場合:(高低差)ー((高低差)ー(1m))×1/2 を減算する。
例えば高低差が2mの場合は 2mー(2m-1m)×1/2=1.5m を減算する。
ステップ5 北側斜線制限の確認
北側斜線制限の場合は北側で決まることが多いので確認する(法第56条第1項第三号)。
- 水平距離は求める点から北側までの敷地境界線まで
- 高さは水平距離×1.25+5m(第一種、二種低層住居専用地域、田園住居地域)
水平距離×1.25+10m(第一種、二種中高層住居専用地域)
以上になります。大体の問題はステップ1~ステップ3で求められる問題が殆どなので試してみてください。思ったより簡単に解けると思います。
最後に隣地高さ制限の式だけ紹介しておきます。
- 住宅系:(水平距離)x1.25+20m
- 商業系:(水平距離)x2.5+31m
隣地高さ制限は距離は水平距離は短いのですが、住宅系なら20m、商業系なら31mを加算するので
道路境界で決まるケースが多いです。最後求めた高さと最後比べる程度で良いです。